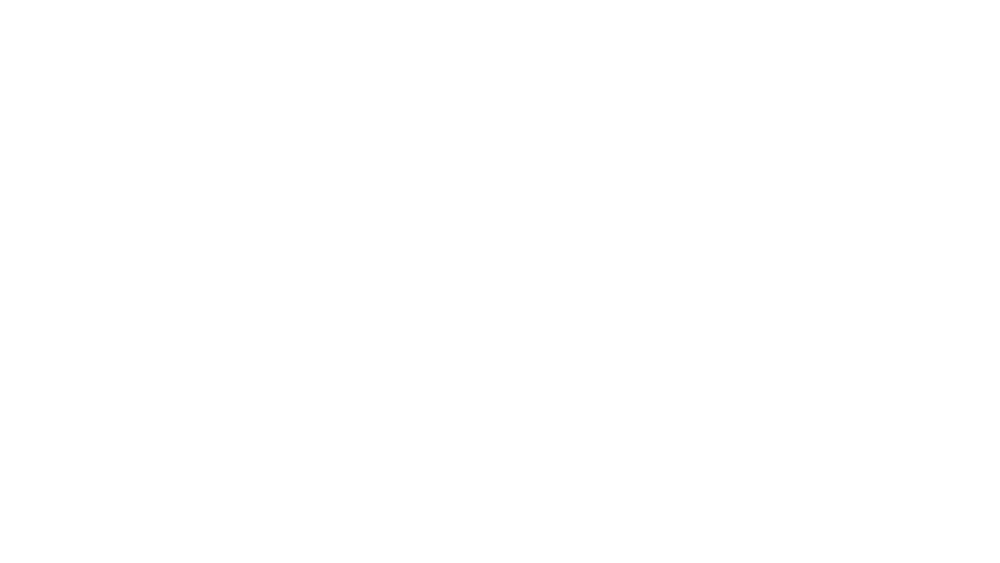日時 2021年8月28日(土) 13:30〜17:00
会場 Zoomによるオンライン配信
開会の辞
研究発表
大久保美花 プロレタリア文学批評にみられる横光利一の感覚論 ―蔵原惟人の感覚論との比較を通して―
日本近代文学史では、昭和初期のいわゆる三派鼎立の時代に、新感覚派とプロレタリア文学のアート対立がつとに指摘されてきた。また両者が衝突した形式主義文学論争の横光利一の言説も、先行研究では具に考察されてきた。こうした初期の横光の創作活動を支えた理念は、言うまでもなく「感覚」である。だがその一方で、横光と論争を交わしたプロレタリア文学者の蔵原惟人もまた、「感覚」という表現をしばしば用いる。マルクス主義思想において感覚の問題は近代的人間の認識の在り方の一つであるフェティシズムにも関わるため重要である。
プロレタリア文学を批評する際に、横光の感覚論はどのように現れるのか。本発表の目的は、プロレタリア文学の感覚論という新たな視点を取り入れることで横光の感覚論を再検討しつつ、横光独自の文学観を抽出することにある。 本発表では横光と蔵原の感覚論を比較する。まず一九二八―二九年に発表された評論を通して、蔵原が感覚という表現を用いる思想的背景を考察する。蔵原は芸術作品に描かれた題材を通して社会の階級格差を読み取りつつ、フェティシズムに陥る芸術家を批判する。また階級闘争を推進する過程で、彼は作家の意図を離れて無意識に革命思想や「プロレタリア的感覚(近代工業的感覚)」を読者に「伝染」させてしまう芸術の性質に期待を寄せる。ここから蔵原にとって「感覚」とは「階級意識」を指すことが窺える。
一方、一九二七―二九年に発表されたプロレタリア文学を論じた評論を対象に、横光が人間の知覚にこだわる意図を考察する。横光はプロレタリア文学の本質を「理論」と捉えたうえで、作家にとって重要なことは論理では掬いとることのできない「個性(愛嬌)」を知覚することにあると述べる。横光において「個性」とは各人の特徴という意味には留まらず、同座する他者と共同製作する、ある種の感情状態である。移ろいやすい感情の流れを読み取り、その世界観に浸る経験は作家―対象間では文体に表れ、作品―読者間では読書経験に現れると横光はいう。ここから横光にとって「感覚」とは「他者との一体感」であることが窺える。
以上、二人の感覚論は人々の情動伝染を扱うという点で立場を同じくするが、蔵原はそれを大衆啓蒙の手段にするのに対して、横光は究極的には他者との一体化を目指すと結論づける。このコミュニケーション観に横光の独自性が存すると本発表では指摘する。
王暁亮 心理主義か人間主義か ―横光利一の存在論的転回と人間学―
新感覚派時代の横光利一の文学論は、従来の先行論においては、言文一致以来の透明な記号観とは異なる、カントの認識論に基づく形式主義として位置づけられてきたが、「新感覚論」における「物自体に躍り込む」、「世界観念へ飛躍せん」などの横光の独自のカント解釈にはキルケゴールの実存哲学の影響がうかがえる。これらカントに収まり切れない要素が重要なのは、今までの「認識論から存在論へ」という枠組みを考え直す契機となるからである。
新感覚派時代からのキルケゴールの影響は、「機械」の書かれた 1930年前後に三木清の人間学的マルクス主義の影響と合流し、横光利一の存在論への転回が本格的に始まる。位田将司が『欧州紀行』に見た構造的な「穴」は、すでに、「機械」の時期に開いていた。屋敷の死を「否定神学的な場所」とする石橋紀俊の「機械」論は直接に言明していないが、まさしく「機械」における存在論的欲求を読み取ったのである。ただし、この「否定神学的存在論」は「穴」を塞ぐかわりに、「穴」の周りを回り続けるがゆえ、認識論と見なしてしまいがちである。今までの「機械」論においては、しばしば〈疎外〉、〈物象化〉などの用語は用いられてきたが、1930年時点のルカーチの物象化論は実は疎外論そのものであり、三木清の人間学と同じく存在論的な性格をもっている。横光もフォイエルバッハを直接に援用し、人間の「類的本質」に当たるものを少なくともこの時期から想定している。〈ポスト68年〉の現代思想から得られる疎外と物象化との間の〈認識論的切断〉は「機械」をはじめとするいわゆる「心理主義」小説における疎外論を物象化に転倒させてしまったと言えよう。
それゆえ、「心理主義か人間主義か」という問いは単なる言葉遣いの違い以上の意味を持っている。三木清が「パスカルに於ける人間の研究」において警告したように、人間学は「心理学」や「認識論」ではなく、「存在論」なのである。しかし、こういう警告自体が、人間学と認識論及び心理学との親和性を逆説的に物語っていることにもなる。本発表はこの「認識論」に取り違えがちな人間学の存在論的志向を横光利一の「機械」というテクストに見出すことをめざす。
小林洋介 横光利一「馬車」における〈個〉の運命と易
横光利一「馬車」(『改造』一九三二年一月)は、〈脳病〉、ハンセン病、易学、温泉での転地療養といった複数のモチーフが絡み合う物語である。「馬車」についての先行研究としては、「すべてをあたたかく受け入れようとする昔の村落共同体と、自然科学の発達に裏付けされた近代的認識によって、すべてのものと対峙していこうとする都会との対比」を読み取る玉村周の論(『横光利一―瞞された者―』明治書院、二〇〇六年六月)、由良の「拡散的〈移動〉」と花江の「反復的〈移動〉」とを読み取る副田賢二の論(「横光利一「時間」「馬車」と〈移動〉のモティーフ―一九三〇年代初頭の同時代現象として―」『横光利一研究』第四号、二〇〇六年三月)がある。さらに高橋孝次「草津湯ノ沢地区と中里介山「夢殿」―横光利一「馬車」の世界―」(『日本近代文学と病』千葉大学大学院人文社会研究科研究プロジェクト成果報告書、二〇〇九年三月)は、「馬車」に描かれた温泉地のモデルが群馬県草津温泉であることを指摘している。だがこれらの先行論はいずれも、「馬車」の主要なモチーフの一つである易については本格的な分析を行っていない。
本発表では、第一に、高橋の研究成果を踏まえ、「馬車」における温泉地の描写の背景に草津温泉があることを示す補足的情報を提示する。第二に、草津湯ノ沢地区に存在したハンセン病患者の集落「鈴蘭村」と、同集落において献身的看護を行った三上千代についての同時代文献を紹介する。第三に、作中の古奈教授が語る易に関する情報の一部が、思想家・遠藤隆吉の著作と照応していることを論証する。その上で、第四に、「馬車」に表れた横光の思想的変遷について考究する。
実在の人物である三上千代は、誤診をきっかけとしてではなく自分の意志でハンセン病患者と共に住み看護を行った。それに対し「馬車」の古奈花江は「癩病」と誤診されたことをきっかけとしてハンセン病患者たちのコミュニティに属することとなる。こうした創作上の操作により、「馬車」においては、医学をはじめとする近代科学では把握しきれない〈個〉の運命が前景化され、さらには、〈個〉の運命を扱う易が価値を持つことになる。そこで本発表では、横光の思想的経歴において、一九三〇年前後の〈心理〉への関心の延長線上に、西洋近代科学への信頼の留保と、易という東洋思想への関心があったことを明らかにする。