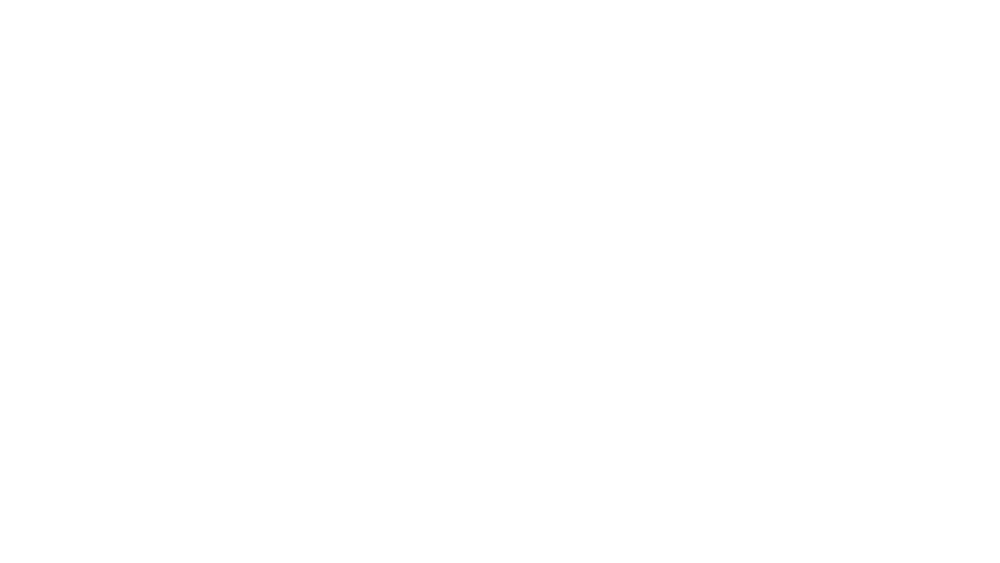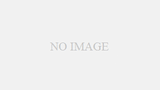日時 2025年3月29日(土) 午後2時~5時(開場午後1時30分)
場所 お茶の水女子大学 共通講義棟1号館 302教室 会場+Zoom配信
※会員はZoomにて、「総会」(午前10時~11時)を行います。
※会場に参加できるのは会員のみです。
※事前にお送りした大会案内状が入構許可証になりますので、必ずご持参ください。
総会 午前10時~11時 Zoomによるオンライン配信
- 横光利一文学会会員限定
- 令和六年度活動報告・令和七年度活動方針ほか
自由研究発表 午後2時~
- 劉 新雲(大連外国語大学大学院)「横光利一「無礼な街」における空間と女性の身体」
劉 新雲 「横光利 一「無礼な街」における空間と女性の身体」
「無礼な街」(『新潮』、一九二四年九月)は、関東大震災後の東京という都市空間(街)に生きる人々の心理や身体感覚を描写した「街もの」の一つである。先行研究では、自我と他者、さらには街における人間関係というテーマに加え、都市としての街という空間についても考察が行われてきた。しかしながら、これらの議論は主に男性主人公である「私」の心理や「私」と街との関係に焦点を当てて展開されているため、女性(「知らない女」や妻)を中心とした考察は依然として不十分である。また、作品内で四回言及される「花」の意味についても、十分に注目されていない。以上を踏まえ、本発表では女性の身体に着目し、「花」という比喩を中心に据えた象徴的な表現を手がかりに、街と女性の身体の関わりを探究することを課題とする。
「花」が象徴する女性の身体表象は、貞操の問題として顕在化するだけでなく、街における人間関係と生活実態の構造を形成する重要な役割を果たしているため、本作のテーマを理解する上で不可欠であると考えられる。一方で、女性の身体表象や「私」の個人生活、さらには生きている都市空間を象徴する「花」という象徴的表現と、「私」の街での往復移動や身体感覚の変化という写実的表現との交錯を通じて、個人、他者、社会が絡み合う入れ子構造が形成されている。このような見立てから、本発表では、「無礼な街」を横光利一の創作過程における「象徴的な小説」から「客観的な写生」への移行を反映した短編小説として位置付ける。本作における象徴的表現と写実的表現を分析し、空間と女性の身体の関わりを明らかにすることによって、「無礼な街」が有する横光利一の初期文学における重要な転換点としての意義を再評価することを目的とする。
特集 横光利一における詩と散文のあいだ 午後2時50分~午後5時
横光利一は小説だけではなく、詩、俳句、短歌と様々なジャンルで創作を行ってきた。定本全集に「詩」として収められた作品は少ないが、随筆「まづ長さを」(一九二九)では自らの新感覚派時代を振り返り、一番最初に書いたのは「詩」であり、そこから「戯曲」を経て「小説」に至ったと打ち明けている。一方、横光はヨーロッパへ向かう船のなかで句会に参加して以来、『旅愁』から晩年の『微笑』に至るまで俳句に関心を寄せてきた。川端康成が絶賛した横光の「蟻台上に飢えて月高し」を俳句と見るか、あるいは短詩形と見るかについては評者によって意見が分かれるが、ここにはどこまでも高き理想を追い求めていこうとする横光の作家としての真摯な態度が窺える。
このように横光の創作の出発点である新感覚派時代の表現が、散文的な発想以前に詩的な語彙や比喩表現を用いたものであることは明らかであるし、一九三〇年代以降における俳句への接近も、横光の詩的なものへの関心だと言えるだろう。こうした横光の志向を一九三〇年代の『詩と詩論』、『詩・現実』などに関わる現代詩への傾斜として捉えることもできる。またその一方で、「皮膚」、「盲腸」といったコント的テクストを、散文詩的な文脈に置くことも可能である。
こうした状況を踏まえると、横光における詩的表現、横光とアヴァンギャルド詩、短詩形と新感覚派的表現などいくつかの接線が見出せるのではなかろうか。
昨年三月、木田隆文編『日本未来派、そして〈戦後詩〉の胎動―「古川武雄宛池田克己書簡」翻刻・注解/詩誌『花』復刻版』(琥珀書房刊行)が刊行されたが、それによれば日中戦争時に上海に渡り、中国と日本で日本文学者のネットワークを作り上げた詩人の池田克己が編み、日本戦後詩の一大潮流を築くことになる詩誌『日本未来派』には、横光の最晩年の詩作品が収められているという。『日本未来派』の編集同人のひとりで横光門下生の一人である菊岡久利と横光の関係も興味深い。
さて、本大会では前掲の著書を上梓した木田隆文氏(奈良大学)をお招きし、横光と『日本未来派』との関係、またそれを取り巻く戦後詩壇の状況についてご講演いただく。それとあわせて本学会からは田口律男が旧制中学時代から最晩年に至るまでの横光の詩作を通して、横光において詩とは何だったかを問い直す。以上、本大会では横光における詩と散文のあいだを問うことで、横光の文学観に新たな光をあててみたい。
【基調講演】
- 木田隆文(奈良大学) 「横光利一の戦後詩―背景としての『日本未来派』」
木田隆文 「横光利一の戦後詩―背景としての『日本未来派』」
池田克己は、戦前の奈良吉野で詩誌『豚』を創刊し、全国の若手詩人の領袖として注目を集めた。日中戦争開戦後は上海に拠点を移し、現地の日本人文学者を糾合した上海文学研究会を結成、機関誌『上海文学』を拠点に大陸各地の文学者と連携を計る。そして敗戦後。彼が鎌倉で創刊したガリ版詩雑誌『花』には、『豚』・『上海文学』同人はもちろん、高見順ら戦前日本/戦時中国で池田と交流を持った文学者が再結集し、やがてそれは戦後詩の一大潮流を築いた『日本未来派』へと発展した。
『日本未来派』は、池田克己を軸に広がった、戦前内地―戦時中国―戦後日本の文学者ネットワークそのものであったといえよう。そして横光利一もまた、その網の目に連なるひとりであった。
『日本未来派』(第四号、一九四七年九月)には、横光の詩「別離」・「桃」「夜長」が掲載されている。この詩が掲載された経緯は詳らかではないが、日本未来派の編集同人であり、横光門下の菊岡久利が仲介役となったと推定される。また横光と日本未来派の人的関係でいえば、同会の配給取次実務は横光に師事した森敦が担当しており、さらには実現こそしなかったものの、池田は日本未来派から横光の詩集を刊行しようともしていた。
そこでこの講演では、上記の横光の詩が掲載された経緯に触れつつ、横光と日本未来派の関係、そしてそれを取り巻く戦後詩壇の状況を素描してゆきたい。またあわせて日本未来派の前身である上海文学研究会と横光「上海」との関係性や、大東亜文学者大会の話題などにも言及できればと考えている。
ちなみに池田は『日本未来派』を「一切の党派や権威を無視したぼうばくたる容積」たらんとした。それと同様、この講演も、戦前/戦中/戦後、内地/外地に跨る雑多なまとまらない話題を集積する形をとることになりそうである。その話題の切れ端が、他の報告や会場全体での議論の手がかりになれば幸いである。
【報告】
- 田口律男(龍谷大学) 「横光利一における詩と背理」
田口律男 「横光利一における詩と背理」
詩とは何か、という根本問題は措くとして、横光利一にとって詩とは何であったかを問い直したい。横光が「一番最初は詩を書いた」(一九二九)という時、その念頭にあったのは、三重県立第三中学校時代に書いた「夜の翅」(一九一六)あたりだろう。この技巧を凝らした象徴詩もどきに、新感覚派の濫觴をみるのは容易い。ただ、そうした傾向性は、敗戦を挟んだ最晩年の詩作(たとえば『日本未来派』に寄せた三篇)にも受け継がれているだろうか。個人的な感想をいえば、そこに持続する横光固有の詩と詩論を想定することは難しい。詩にも横光のゆらぎが刻印されている。
一般に、詩は散文より文法や統辞法から自由であり、物語内容やプロットの制約を受けにくい。また、定型や伝統を上書きしつつ発展する俳句や短歌とも異なり、言葉に内在するリズムやイメージが横溢する傾向にある。さらに、第一次世界大戦前後の前衛芸術の荒波を受けた現代詩は、既存のパラダイムを次々に破壊した結果、より混沌に向かっていったことはよく知られている。「……だれもかれもが道ばたで金塊を拾うようにポケットにエスプリをいっぱいつめこんでいた。みんなエスプリがありすぎて、困つたような時代だつた」(一九五一)とは、『詩と詩論』のオルガナイザー春山行夫の回想である。
横光の詩のいくつかには、身心に沁みついた旧い詩想とリズムが露呈しており、横光の生地がより滲出しているようにも見える。とはいえ、「国語との不逞極まる血戦」に挑んだ横光にとって、たとえ主戦場ではなかったとしても、詩がその「血戦」にどう関わったかを問うことは無駄ではない。詩人に選ばれなかった横光が、佐藤一英・北川冬彦・菊岡久利・宮沢賢治といった詩人に強く共振した理由についても考察できればと念じている。