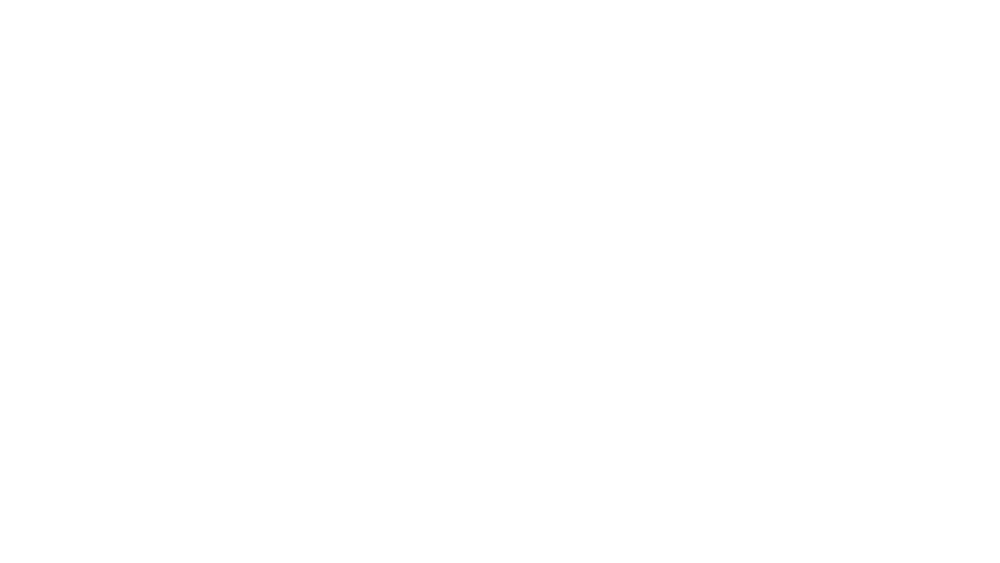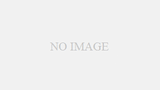日時 2025年9月6日(土)13:00~18:00
場所 龍谷大学深草キャンパス(慧光館2階201教室)+Zoomによるオンライン併用
→キャンパスマップ19番の建物です。
- 非会員の方も自由に参加できます。(対面・Zoomによるオンライン配信、どちらでも可。)ただし、こちらのフォームより、事前にお申し込みください。期限は9月5日(金)正午とさせていただきます。→受付を終了しました。
- 対面参加の方は、当日も受け付けます。
開会の辞 運営委員長 黒田大河
研究発表
横光利一「七階の運動」(『文藝春秋』、一九二七・九)は、関東大震災後の都市空間に普及しつつあった架空の七階建て百貨店(デパートメント)を舞台に、「永遠の女性」を創造しようとする久慈と七人のショップガールとの関係を描いた「街もの」の一作である。
「エレベーターは吐瀉を続けた」、「紙幣行進曲に合せてデパートメントは正午へと沸騰する」――というように、この百貨店は、人間の活動をも制御する人工的かつネットワーク的な環境、すなわち「環世界」として表象されている。先行研究は、階層性の批判やジェンダー論、さらには近代制度への批判に焦点を当ててきたが、百貨店という新たな空間と女性の身体性については、管見では十分に論じられていない。本発表では、作中の百貨店をユクスキュルの「環世界」という観点から捉えなおし、女性の身体が断片化され、「永遠の女性」という虚構的存在に変換されていく過程に注目してみたい。
「一ヶ月に二万円」を浪費する久慈は、金銭や資本によってすべての物質が動かされる「百貨店の法則」に同期している。また、七人のショップガールたちも、久慈の「永遠の女性」を構築するための単なる部品として扱われている。言い換えれば、久慈や女性たちは脱人格化され、百貨店という人工的な環境の一部に組み込まれている。しかし、 「頭」として選ばれた能子だけは、「万国の労働者よ団結せよ」と呟き、久慈の法則に抵抗し、百貨店からの脱出を試みる。しかしそれは、百貨店という「環世界」から、異物として排除されることを意味してもいる。
本発表は、同時代資料を参照しつつ、百貨店の文化史的・建築史的意味を確認したうえで、「七階の運動」のテクスト分析を通じて、百貨店という「環世界」と身体との錯綜する関係性を明らかにしながら、初期横光利一の文学的位相の一端を明らかにしたい。
「鞭」(『中央公論』、一九三〇・九)は、一等船客の乙竹順吉が船内で服毒自殺した経緯を、事務長の「私」が説明する物語である。この作品は「機械」(『改造』、一九三〇・九)と同時期に執筆・発表され、いわゆる「意識の流れ」を表した特徴的な文体が注目されてきた。
「鞭」は旅客船の事務長を主人公とし、国際定期船での死亡事故という特殊なケースを舞台とするが、「私」の「心理」を究明していくうえで、「船」や「海」といった「私」を取り巻く環境が及ぼす効果については分析されてこなかった。また、河田和子(二〇〇一)や劉妍(二〇一五)らの調査によって、作品内の「船」は日本郵船株式会社の「日華連絡船」だと明らかにされてきたが、「船」や「海」という舞台が作品に与える効果についても検討されてこなかった。
そこで、本発表では同時代背景に注目し、「船」と「海」の「習慣」の解像度を上げることで、「私」の語りに内在する〈心理〉を再検討していく。具体的には以下の方法をとる。まず、「日華連絡船」に関する調査を踏まえ、「船」という舞台が作品内の連続性を生じるように機能していることを確認する。次に、「私」の語りで執拗に繰り返される事柄に注目し、それが〝聞き手〟(読者)の読みを潜在的に方向づけていることを指摘する。そして、「船員法」や「海員懲戒法」など当時の海事法や海事審判制度を確認し、「私」の「事務長」としての「職責」や「習慣」を具体化していく。そのうえで、海員審判という背景を考慮したとき、「私」の語りが従来と異なる〈心理〉を示し、「信用できない語り」として浮かび上がる可能性を指摘したい。
このように本発表では、〝聞き手〟の背景理解によって「私」の語りの表す〈心理〉の見え方が変わることを指摘することで、「機械」の陰に隠れ続けた「鞭」の再評価を試みたい。
ラウンドテーブル 海の上の横光利一―欧州航路の再検討―
特集趣旨
一九三六年の欧州行が横光利一にとって転機となったことは『欧州紀行』『旅愁』の検討から明らかにされてきた。例えば井上謙・掛野剛史・井上明芳編『横光利一欧州との出会い―『歐洲紀行』から『旅愁』へ』(二〇〇八、おうふう)では「歐州メモ」の翻刻を中心にパリ体験の詳細が論じられた。しかし、欧州への途上で横光の意識がどのように西欧に対抗して形成されたか、その分水嶺は必ずしも明らかではない。そこで今回のラウンドテーブルでは、欧州行の往路として、日本郵船箱根丸での航路体験に焦点を置き、同乗した高浜虚子、上ノ畑南窓(同船機関長)などと共に催された洋上句会や、航路上での作家の心境の変遷などを再検討したい。
特集はラウンドテーブル形式とし、まずは南米移民研究と南米航路に詳しい根川幸男氏から大阪商船と日本郵船の比較や、当時の船上での文化人の交流など、航路文化の観点から横光の航路体験をめぐってご講演をお願いする。後半には二名からの報告を含め、ディスカッションにおいて横光の欧州体験のあらたな知見が得られればと願う。
「欧州紀行」や「旅愁」に描かれた横光利一の航路体験を起点に、近代の日本人がたどった欧州への道のり、日本船に乗り、欧州航路を旅することの歴史的意味について考えたい。すなわち、横浜・神戸からマルセイユ・ロンドンまでの長い航海、門司・上海・香港・ペナン・シンガポール・コロンボ・アデン・マルセイユといった寄港地、魔のマラッカ海峡、灼熱のインド洋などの様子を点描的に紹介する。また、これらの地名や海域が、当時の中等教育を受けた知識人の多くにとって、すでに既知のものであった点について確認する。それとともに、「洋行」「航路」「船上の女」「等級(クラス)と運賃」「洋上句会」といったキーワードから、海と陸地とのあいだに生起する特異な人間関係や文化的営為についても、いくつかのエピソードを交えてお話したい。さらに、横光作品の評者であり、自身も欧州航路を旅した文芸評論家・古谷綱武をめぐる人脈についてふれたい。太宰治、木山捷平、檀一雄、大岡昇平、中原中也、小林秀雄らが群がり、『白痴群』『海豹』『鷭』などという同人誌を生み出した、いわゆる古谷サロンと南米ブラジルとの海を介したつながりについて言及する。
本報告は、横光作品について分析・批評したりするのではなく、そこから派生して、移植民史を専門とする報告者が、海を移動した近代日本人の視点から、文学研究者である皆さんにちょっとした話題を提供する程度の内容とお考えいただきたい。
横光利一「解説に代へて(一)」(『三代名作全集 横光利一集』河出書房、一九四一・一〇)には、「震災直後わが国に初めて生じた近代科学の具象物」として、「自動車といふ速力の変化物」や「飛行機といふ鳥類の模型」の存在を挙げ、「焼野原にかかる近代科学の先端が陸続と形となつて顕れた青年期の人間の感覚は、何らかの意味で変らざるを得ない」と記されている。たしかに、「頭ならびに腹」(『文藝時代』一九二四・一〇)には、内容・文体面含め、特別急行列車に代表される新しいスピード感覚が書き込まれ、「鳥」(『改造』一九三〇・二)では、これまでの時代では体感し得なかったであろう飛行機から地上を見下ろす視線が描出されている。一九三六年の欧州体験でも、往路は日本郵船の欧州航路、復路はシベリア鉄道(加えてヨーロッパ滞在中、飛行機も数回乗っている)と陸・海・空それぞれの交通機関を利用していた。こうして考えてみると、横光利一文学は、同時期の交通インフラの発展と普及を抜きにしては成立し得なかったことだろう。
本発表では、こうした交通機関と横光文学との関わりを概観した後、横光が欧州航路で体験した海という場について考えていきたい。注目したいのは、横光が箱根丸での海上生活を過ごしていく中で、「地上の理智」と「海上の理智」といった考えを『欧州紀行』(創元社、一九三七・四)に記している点である。船内での生活や当時話題なっていた熱帯季語という問題、帝国列強の海洋戦略などの世界史的背景も参照しつつ、「地上の理智」と「海上の理智」の内実を見定めていきたい。そして、海上体験で得た知見がどのように後年の作品や評論に展開されていったのか、特に「旅愁」(『東京日日新聞』一九三七・四・一四―八・六ほか)や「微笑」(『人間』一九四八・一)に描かれていく〈空〉への関心との繋がり(もしくは発展)についても論じていく。
宮崎市定は一九〇一年生まれ、横光利一とほぼ同世代の東洋史学者である。一九三四年に京都帝国大学文学部助教授となり、一九三六年から文部省在外研究員としてフランスへ留学した。欧州への往路、箱根丸にて高浜虚子の洋上句会に参加し、横光と知り合った。
宮崎の専門は中国の歴史であるが、その興味の赴くところは広汎である。帰国後、戦時下の著作に限ってみても、日本と中国の関係、あるいは東洋と西洋の関係、そして東西両文明のはざまにある西アジア古代文明への強い関心。日本と東洋を世界史の中にいかに位置づけるか、それは時代に要請された問題意識でもあった。
横光は宮崎と親しく語り合うことはほとんどなく、帰国後に宮崎の著作を『旅愁』執筆の参考にしたということもなさそうである。しかし、宮崎との出会いが横光に何らかの作用をもたらし『旅愁』の矢代という人物が生み出されたのであろうし、矢代の人物設定の一部分は宮崎市定に由来していると言える。
今回の報告では、横光と同時代を生きた一人の歴史学者の欧州体験とその著作を参照することで、『旅愁』に書かれなかったことをあえて探究してみたい。それは『旅愁』を俯瞰する新たな手がかりとなることだろう。