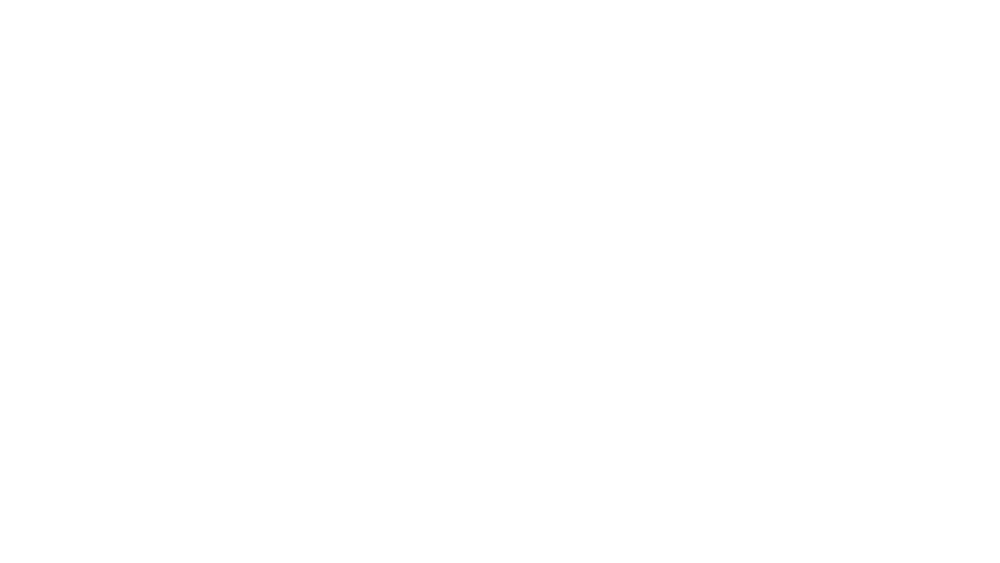日時 2023年9月2日(土)13:00~18:00
会場 龍谷大学大宮キャンパス(東黌303教室)+Zoomによるオンライン併用
開会の辞
特集 1923――『文藝時代』前夜――
本年は関東大震災から一〇〇年目である。震災の翌年一九二四年一〇月、『文藝時代』の創刊を契機とし、震災後文学ともいわれる新感覚派が誕生した。現代につながる都市風景が震災後の復興と共に生じたことを背景とし、第一次世界大戦後の世界の潮流と日本の詩壇、文壇、画壇など共鳴する時代が前史として生じていたことも大きな要因と考えられる。
一九二三年に焦点を絞ってみても、稲垣足穂『一千一秒物語』、高橋新吉『ダダイスト新吉の詩』、萩原恭次郎らの『赤と黒』の創刊、そして横光利一には「日輪」、「蠅」、川端康成には「会葬の名人」があり、新感覚派の前史と見られる活動が盛んになっていたことが分かる。
本特集では『文藝時代』前夜に焦点を当て、震災一〇〇年および『文藝春秋』創刊一〇〇年をも視野に入れ、多角的に新感覚派の前史を検討してみたい。そこには文学革命と革命文学とされる新文学の二つの潮流が混沌とした姿で横たわっているだろう。横光が『文藝春秋』創刊号で「時代は放蕩する」と宣言した時代感覚は、一〇〇年後の今日にもなお振動し続ける時代の断層を指し示しているのではないか。
会員外からは吉岡洋氏(美学芸術学 京都芸術大学)をお招きし、一九二三年の諸作品を取り上げながら、モダニズムの根底に生じていた時代の変化と哲学、および思潮について、文化史的な観点からお話しいだだく。会員からの発題とあわせて、革命前夜を明らめるディスカッションが行われるであろうことを期待したい。
基調講演
甲南大学教授、情報科学芸術大学院大学(IAMAS)、京都大学文学研究科教授、同大学こころの未来研究センター教授を経て、京都芸術大学文明哲学研究所教授。カントを中心とするヨーロッパ思想、現代哲学、メディア論を中心に研究。著書に『情報と生命』(新曜社)、『〈思想〉の現在形』(講談社)他、美学芸術学、情報文化論に関わる著作、翻訳など多数。批評誌『ダイアテキスト』(2000-2003、京都芸術センター刊)編集長、『京都ビエンナーレ 2003』、「岐阜おおがきビエンナーレ 2006」他の総合ディレクターとして企画を行う他、映像インスタレーション作品「BEACON」の制作にも加わってきた。文化庁世界メディア芸術会議(IGOMAG、2011-2013)座長。前・美学会会長。日本学術会議会員(哲学委員長)。
研究発表
横光利一「日輪」の発表状況を問いなおす 島村 健司
本報告の趣旨は、標題どおり横光利一「日輪」の発表状況を問いなおすことにある。この趣旨で考えてみるのは、つぎのようなことによる。横光の文壇デビューは、一九二三年五月、「日輪」(『新小説』)と「蝿」(『文藝春秋』)を同時期に発表したことと解される。この両作が発表された翌年、『讀賣新聞』(一月二一日付「月曜附録」)に横光のエッセイ「黙示のページ」に付帯するように「自己紹介」という見出しの文章が掲載される。ここには横光の胸上写真が組み合わされている。この写真のキャプションには「新進作家の花形◇横光利一氏◇」とある。つまり、新進作家として華々しくデビューした横光自身が自己紹介をおこなっているというイメージが大衆紙によって流布されるような格好といえるだろう。この「自己紹介」で横光が記す小説は、「日輪」のみとなっている。このようになっている経緯を「日輪」の発表時期に立ち返って問題提起したい。
「一千一秒物語式の市街」の造形
──稲垣足穂と横光利一その周辺── 高木 彬
横光利一が一九二二年に創刊した同人雑誌『塔』(第二号で廃刊)の表紙に掲載された都市の図像の出典は、トマス・ド・クインシー『阿片溺愛者の告白(The confessions of an English opium-eater)』(原書)中の挿絵である。その同じ挿絵の場面をモデルとして、稲垣足穂は「緑色の円筒」(一九二四年)で「一千一秒物語式の市街」を造形した。ただし、横光が『塔』の表紙にその挿絵を用いていたことを足穂が知るのは、「緑色の円筒」を発表した後だった。このニアミスからわかることは、すでに彼らは『文藝時代』同人となる以前から、都市や造形への感受性のいくらかを共有していたということである。(この列には、石野重道、近藤正治、平岩混児といった関西学院で足穂と同窓の詩人たちや、一九二二年創刊の『エポツク』(後に『ゲエ・ギムギガム・プルルル・ギムゲム』へ移行)で活動していた野川隆も加えることができるだろう。)また、こうした都市・建築表象は、山田守や瀧澤真弓ら東京帝国大学建築学科の卒業生たちによって一九二〇年に結成された分離派建築会による図面・模型と、造形的に近似している。本報告では、こうした共振の様相を検討した上で、分離派のアヴァンギャルド建築が実作の機会を得ていく関東大震災(一九二三年)後の復興期において、横光や足穂らの紙上都市がいかなる批評性を持ちえたのかを明らかにしたい。