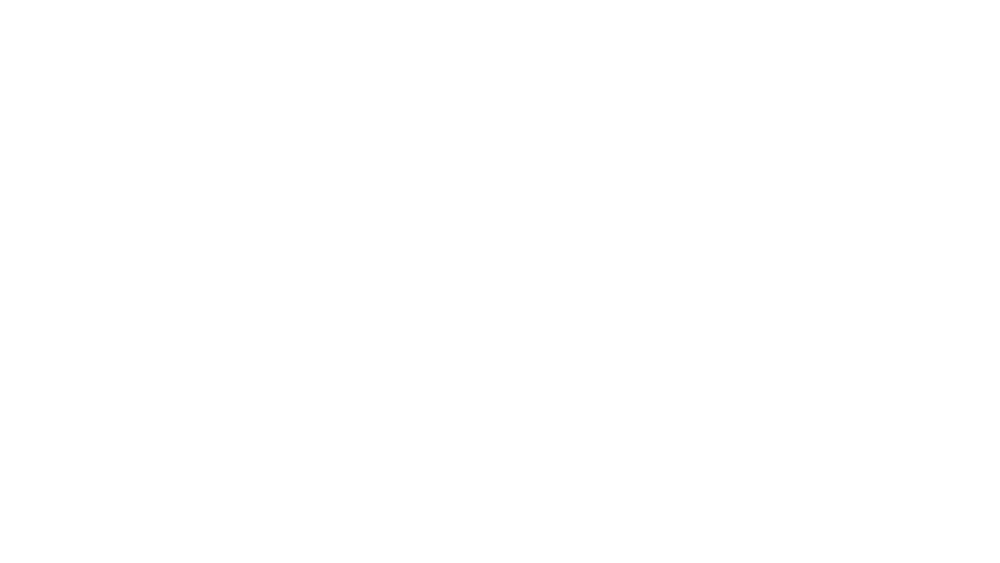日時 2023年3月18日(土)13:00-18:00
会場 武蔵野大学武蔵野キャンパス(1号館1階1102教室) Zoomによるオンライン併用
総会(11:00より)
- 令和四年度活動報告・令和五年度活動方針ほか
開会の辞(13:00より)
- 中村 三春(北海道大学)
会場校挨拶
- 土屋 忍(武蔵野大学)
研究発表(13:10より)
- 中村 梨恵子(同志社大学大学院) 『花園の思想』論―〈空間〉と〈人物の移動〉から―
中村 梨恵子 『花園の思想』論―〈空間〉と〈人物の移動〉から―
横光の一連の病妻小説の中でも最後に発表された「花園の思想」(一九二七年二月)は、唯一、妻が亡くなる瞬間を記述してみせた作品である。本作と他の病妻ものとの大きく異なる特徴としては、〈空間〉と〈人物の移動〉が挙げられる。妻と彼女を看病する夫が共に閉鎖的な場所に留まるのではなく、〈空間〉から〈空間〉へと移動する夫、そして「病室」という〈空間〉に留まる妻が描かれる。これら作中の〈空間〉の扱いが「花園」に象徴的な意味をもたらし、最後に、直接描写することが不可能だった「死」を、妻の「死」を目の当たりにした直後の夫の〈空間〉の移動によって、描き出している。
既に「花園の思想」については多くの研究が試みられており、「花園」「漁村」をはじめとする〈空間〉が果たす役割についても、随所で指摘され、特に象徴的な〈空間〉として「花園」が形成される仕組みと共に論じられてきた。しかしながら、その多くは「花園」と「漁村」の二項対立的な構成にほぼ回収され、花壇、サナトリウムの建物、妻の病室、看護婦部屋のような細部の〈空間〉については、「花園」に付随するものとして触れられるに留まる。
本発表では、夫や看護婦たちの〈移動〉や、夫の「病舎の方を振り返る」といった身体表象と、〈空間〉とを結びつけそれらの〈空間〉が果たす役割を考察する。たとえば、夫が眺めている光景の記述には、擬人法や比喩をふんだんに用いた「新感覚的」な情景描写が用いられているが、それは単なる技法上の表現ではなく、それぞれの〈空間〉の役割や関係を構築していく上で、重要な意味をもつ記述なのである。 いわゆる病妻ものという「私小説的」な題材を「新感覚的」な描写表現によって昇華したと評価される「花園の思想」であるが、本発表では、〈空間〉と〈人物の移動〉という観点から、横光が「死」そのものを記述するために採った方法を明らかにしたい。
小特集 子どもの表象(14:00頃より)
横光文学における「子ども」(少女・少年などを含む)の表象について考える。そこにはどんな認識や表現の傾向性が認められるだろうか。例えば「笑われた子」の主人公は夢の中で見た「面」に支配される。他者によって左右される生の有様には、現代のあるべき「子ども」像とは異なる可能性が見られる。「蠅」の男の子、「頭ならびに腹」の子僧、「赤い色」の少年、横光作品の「子ども」表象の持つ可能性を問いたい。先行作家や同時代作家と対比しながら、家族、身体、ジェンダーといったミクロポリティクスに注目し、現代日本の子どもをとりまく諸問題に接続する。教育や児童文学の問題とも交錯するディスカッションを期待したい。
重松 恵美(梅花女子大学) 小川未明と横光利一―少年の悲哀と憧憬―
野中 潤(都留文科大学) 横光利一文学のなかの子供を読む →特設サイトを作成しました。
ディスカッサント 藤本 恵(武蔵野大学) 司会 小林洋介(比治山大学)
小特集のための質問フォームを作成しました。
重松 恵美 小川未明と横光利一―少年の悲哀と憧憬―
横光文学の「子ども」の表象を考えるという今回の企画に、なぜ小川未明を取り上げるのか。実は未明と横光には明治大正期の経歴に接点もあり、作品に類似性もある。父が家族と離れて暮らした時期があり、初期作品に寂しい母のモチーフが見られること。横光には姉があり姉弟ものの作品があるが、一人っ子の未明にも初期から姉弟ものがあり、幼少期の年上女性への思慕が背景にあること。地方の城下町で中学時代を過ごし下宿生活を経験していること。中学時代は共に数学が苦手であったこと。横光の恩師・島村嘉一が未明と同時期に早稲田英文科に在籍しており、横光も早稲田英文へ進学したこと。
今回は主に未明の初期小説を扱うが、例えば、「麗日」(1908)には「父は私の生た時も家にゐなかつた。(略)私は母の手一つで育ったのである。」とあり、「越後の冬」(1910)には「太吉の父親は病身の妻と其の子を残して、上州へ出稼に出たのである。」とある。「漂浪児」(1904)には「嗚呼世間に幾何も親しい姉弟はあるが、恐らく私と姉さん見たいに仲の善かつたものは何処にあらうか。」とあり、「霙に霰」(1905)には「村里先生といふのは、二十五六歳の女教師で(略)私は何いふものか心の底から村里先生が慕しくつて、折々夢にさへ其の面影を見たことがある。」とある。これらは母や姉、年上女性を描いた作品群であるが、「懐旧」に登場する十七歳の少年は、城下町の漢学塾に下宿しており、友人の吹く明笛の音色に涙し、年下の少女との出会いを夢見ている。これらを横光の「火」「姉弟」や「雪解」と比較検討してみたい。また、数学が苦手で小学校をやめさせられた桶屋の子が家業を継ぐことになり劇薬を飲んで死ぬ「少年の死」など、子どもの病や死、働く子どもを描いた作品と横光作品の類似性にも論及してみたい。
野中 潤 横光利一文学のなかの子供を読む
ちょうど私が浪人生活を送っていた一九八〇年に、「児童の発見」を収録した柄谷行人の『日本近代文学の起源』と、フィリップ・アリエスの『〈子供〉の誕生―アンシァン・レジーム期の子供と家族生活』の邦訳が出た。大学で文学研究というものに出会う中で、さまざまな事柄の自明性を疑い、問い直すことを学んでいくことになった八〇年代はじめ、柄谷行人やアリエスに導かれながら「子供」というものの自明性をカッコにくくることを知った。
横光利一の文学に初めて触れたのも、ちょうどそういう学びのステージのさなかであった。ところが、横光利一を「子供」という観点を念頭に読んだことは、どうやらこれまでなかったようだ。ただ、あらためて思い起こしてみると、「火」(1919)、「面(笑われた子)」(1922)、「蝿」(1923)、「御身」「頭ならびに腹」「赤い着物」(1924)など、初期小説には「子供」たちが印象深い表象としてしばしば登場する。また、後年の「機械」(1930)に登場する「主人」や、「微笑」(1948)に登場する「栖方」の「無邪気さ」の中にも、「五つになった男の子」や「童顔」を見出すことができる。そしてそれらには何かしら、横光利一文学ならではの特徴がありそうな気がする。とは言え、横光利一の文学全体を「子供の表象」という観点から読み直すというのは、今の私の手に余る。そこで、今回は、何かしら特定の小説に焦点をあてて(「面」を取り上げる予定である)、「横光利一文学のなかの子供を読む」ということにしたい。
近年は、「文学研究」というものから距離を置き、国語教育、とりわけ教育ICTの活用に関しての取り組みで月日を過ごしてきたが、こうした機会をいただいたので、文学や教育をめぐる環境の変化をも視野に入れ、「読むこと」や「発表すること」のあり方にも一石を投じるような「小特集」の「発表」にしてみるつもりである。
公開インタビュー(16:00頃より)
【公開インタビュー】 作家・翻訳家 アンナ・ツィマ 氏
――話題作『シブヤで目覚めて』の著者に訊く――
インタビュアー 田口 律男・中井 祐希・芳賀 祥子
アンナ・ツィマ氏のプロフィール
一九九一年、チェコの首都プラハに生まれる。カレル大学日本研究学科を卒業後、日本に留学。現在はカレル大学大学院博士課程に在籍し、日本で創作、翻訳、研究活動を行なう。二〇一八年に長編小説 Probudím se na Šibuji でデビューし、マグネジア・リテラ新人賞などを受賞。各国で翻訳され、二〇二一年に『シブヤで目覚めて』(河出書房新社、阿部賢一・須藤輝彦訳、二〇二一)が刊行される。
二〇二二年、第二作となる Vzpomínky na úhoře(邦訳『うなぎの思い出』)をチェコで刊行。翻訳には、高橋源一郎『さようなら、ギャングたち』(イゴール・ツィマ共訳、二〇二一)、島田荘司『占星術殺人事件』(イゴール・ツィマ共訳、二〇二一)、漫画『とつくにの少女』(二〇二二〜)などがある
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
『シブヤで目覚めて』は、日本文化に魅入られた大学院生ヤナ・クプコヴァーが、プラハとシブヤに分離しつつ、協力者たちに助けられながら、架空の作家「川下清丸」に肉薄していく物語です。内容/形式ともに複雑な仕掛けに満ちた長編小説ですが、なんといっても虚実の入り混じった横光利一関連情報が巧みに織り込まれていることに驚かされます。『文芸時代』に掲載されたという川下清丸の作品「恋人」を断続的に翻訳していくシークェンスは、物語内容を多層化し、読者を時間・空間の迷宮に誘います。
当日は、著者を交えて、作品の理解を深め、その魅力を最大限に引き出します。