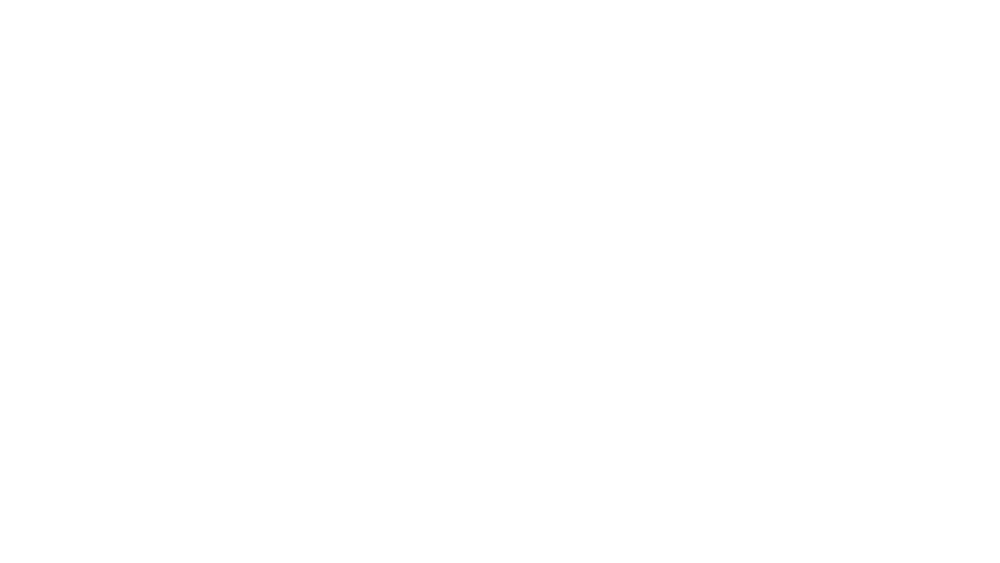日時 2022年8月27日
会場 Zoomによるリモート開催
開会の辞
研究発表
横光文学における認知の思考――病妻小説を端緒として―― 英 荘園
横光の病妻小説は、周知の通り、最初の妻キミの病死という実体験に基づき、数多くの先行研究が存在する。先行研究のうち、早期の言説の多くは、横光の妻に対する愛情に焦点を当てたものであった。一九七〇年代後半、作品論が本格的に展開されるようになると、妻に対する愛情を主張する説は消え、主人公の内面に注目する説が出現しはじめる。妻への愛情を認める言説も、夫の内面を強調する言説も、問題を病妻というテーマに限定する点で等しい。
しかし、キミの病状が悪化する前に、横光はすでに両親の死を経験していた。そして、その経験をもとに、「青い石を拾つてから」(『時流』、一九二五年三月)という父の死をモチーフとする小説、「無常の風」(『文藝春秋』、一九二五年九月)という両親の死に言及するエッセイを発表している。キミの没後は、「春は馬車に乗つて」(『女性』、一九二六年八月)などの病妻小説を創作・発表するが、それと並行して、「青い石を拾つてから」を焼き直し、「青い大尉」(『黒潮』、一九二七年一月)を発表している。こうした流れをふまえれば、病妻小説は、横光文学から独立したものとは考えがたく、近親者の死というテーマで一連の作品を再解釈する必要があると考える。
本発表では、右の問題意識に基づき、親族の死を描く横光文学に共通する、以下の三つの思考について指摘する。一、「観念」で物理現象を定義することを拒み、あらゆる事象を、「物質の変動」の結果とみなす思考。二、人間の意識、あるいは認知を、身体器官の機能として解釈する思考。三、身体器官として物質化される人間の意識は、「物質の変動」である運命に逆らえないという思考。
近親者の死を次々と経験した横光は、「「死とは何だ。」ただ見えなくなる」(「春は馬車に乗つて」)と思い、死者ではなく、自分の「五官」(「青い石を拾つてから」)と「物の観じ方」(「蛾はどこにでもゐる」(『文藝春秋』、一九二六年十月))に目を向け、自分の身体を「一本のフラスコ」(「春は馬車に乗つて」)とみなし、自身の苦痛を観察することを通して、認知の本質を理解しようとした。病妻や亡父というモチーフは、こうした思考実験の材料である。この思考実験の過程で形成された感覚器官の理論は、新感覚の文学論につながっていく。
横光利一の日本回帰――『恢復期』における「気学」を例に―― 大久保 美花
横光利一の作風は新感覚派、新心理主義を経て、最終的に「日本回帰」に到達すると、先行研究では指摘されてきた。横光の日本回帰の中心には、周知のとおり『旅愁』がある。本発表では『旅愁』第二篇と第三篇の間に発表され、横光の大作創作への決意が窺える短編小説『恢復期』(『改造』第二三巻第七号、一九四一・四)を取りあげる。その際、本作品に描かれた「気学」という特殊な学問に焦点を当てる。
横光は文壇登場期から土地が民族に与える影響に関心を抱き、マルクス主義思想を受容後、それは固有の風景に対するフェティシズムとして現れる。さらに一九三〇年代になると、それは西洋中心主義への反動から日本精神というイデオロギーへと発展してゆく。本発表ではこうした横光の変化を踏まえつつ、『恢復期』における「気学」を例に横光の日本回帰の根底にある風土の問題に言及する。
『恢復期』には作品のタイトルが示唆するとおり、小説家梶の体調が回復するという主題と、若き友人たちとの交流を通して、小説を創作する意欲を取り戻すという二つの主題がある。梶の心身の変化に影響を与えるのが「気学」である。「気学」とは「むかしから日本にある純粋な科学」で、個人の性質と土地や方角が調和しているとその人は幸福になれるという。だが梶によると、あえて調和しない方角に進む覚悟も小説家には必要である。このように本作品において創作と地理的条件は密接に結びついている。
では、『恢復期』において「気学」は横光の文学観をどのように反映しているのだろうか。本発表では、梶を中心に「気学」をめぐる登場人物たちの語りを分析する。その目的は横光の「日本回帰」を風土という観点から再検討することにある。
考察を通して、横光にとって「気学」とは一般に作家個人に帰属すると考えられる創作意欲ですら風土に根差しており、そのことに自覚的になることで大作完成を目指す芸術至上主義の象徴であると指摘する。横光は「純粋小説論」以降、日本の特殊な心の在り方を追求することで、却って普遍的な日本文学の確立を目指した。こうした横光の日本回帰は純粋に創作への熱意によるものとはいえ、民族を地理的条件から理解し、第二次世界大戦下において軍事侵攻に理論的根拠を与えた地政学へと接近するという危険性を持つ。このように本発表では『恢復期』における「気学」を例に横光の「日本回帰」の独自性と陥穽を指摘する。
特集 徹底討論 『微笑』
『微笑』(一九四八・一『人間』)は遺作であるが故に、横光利一の短い戦後を捉える断層を抱えている。「排中律」に象徴される東洋と西洋の断層、戦中と戦後の断層、言論統制下の報道と〈噂〉の断層、そして戦後検閲によってもたらされたテクスト自身の断層。読み返すたびに謎の深まるテクストの深層を、〈プロパガンダの文学〉の視点から五味渕典嗣氏に、科学史の視点から加藤夢三氏に考察を願い、参加者の討論によって読み深めたい。
テクノクラートたちの戦後――『微笑』の倫理―― 加藤 夢三
戦後日本の再出発は、何より科学技術の平和利用の機運とともに始まったと言えるが、その際には広義の理科系知識人たちが、あるべき国土再建の担い手として重要な期待を向けられていた。しかし、そこには戦時下において行政へと精力的に参画し、統治権力にも深く携わった職業技術者(=テクノクラート)たちの戦争責任が忘却されている。とりわけ、彼らは取り立てて右傾的な政治イデオロギーを有していたというよりは、往々にして純粋な知的欲求に支えられた〝善良〟な意思を持っていたものの、その〝善良〟さこそ堅牢なテクノファシズムの母胎となりえていたことが、近年の科学史研究では明らかとなっている。だが、まさにその〝善良〟さを免罪符とすることで、一部の指導的立場にあった僅かな者たちを例外として、概ね戦時下のテクノクラートたちは、戦後の言論空間を巧妙に延命していくことにもなる。
横光利一の遺作『微笑』には、天賦の才覚を持った栖方という職業技術者が登場するが、その描かれ方には、図らずも前述のような戦中/戦後を跨いだテクノクラートの存在が、密かな影を落としている。随所で「少年の面影」を持つことが強調される栖方は、卓越した研究能力によって「殺人光線」の製造を企てつつも、結末では敗戦とともに「発狂死亡」するという劇的な最期を遂げるが、その特異な人物造型には(一見すると政治イデオロギーとは無縁の)無垢さや純真さこそ、時局において帝国日本への狂乱的な献身性を導いていたという皮肉な事態が、きわめて寓意的な仕方で刻まれている。従来、横光の国粋主義への近接は、長篇小説『旅愁』を初めとして、どちらかと言うと観念論的な思想動向のなかで語られがちであったが(そういう側面が強かったことは間違いないが)、併せてそうした〝理念先行型〟の国粋主義だけでなく、ある一人の職業技術者の振る舞いが歪んだ暴走を始めていくまでの行程にも、その痕跡は確かに忍び込んでいたと言える。
他方で『微笑』には、右に示したような危うさとともに、これも『旅愁』から受け継がれた「排中律」批判のモチーフが幾度も書き込まれているが、そこには戦後論壇における職業技術者の功罪をめぐる単純な二項対立に抗う視角をも読み取ることができる。本発表では、こうした多面的な相貌を持つ『微笑』の奥行きを再検討することで、横光晩年の〝戦争責任論〟として、その論理的結構の在り処を解き明かしてみたい。
幻影の強度――横光利一『微笑』を読む―― 五味渕 典嗣
黒田大河や中井祐希がすでに指摘したように、『微笑』の若き数学者「栖方」が開発に携わっていたという「殺人光線」は、アジア太平洋戦争期の日本陸海軍が実際に研究を始めていたものだった(黒田『横光利一とその時代』和泉書院、二〇一七年。中井「それでも最期は微笑を浮かべて」(『國文学論叢』二〇二一年二月)。自らも陸軍登戸研究所で「怪力光線」研究に関与した元技術院総裁・八木秀次は『読売報知』の取材に、日本軍が研究していた「殺人光線」をめぐって、「実験中だった一科学者はその光力のために遂に発狂してしまった」というエピソードを紹介している(「千米隔て敵を殺す “日本の殺人光線”語る八木博士」一九四五年一〇月二八日)。また、植木不等式『ぼくらの哀しき超兵器』(岩波書店、二〇一五年)によれば、当時毎日新聞の社会部長だった森正蔵が、先の記事が掲載された翌日に、盛岡支局から類似の情報を受け取っていた。戦争末期、湯川秀樹門下の二一歳の青年科学者が、「八万メートルを距ったところから発射して空を飛ぶ飛行機、行動中の軍艦などをめちゃくちゃに破壊する新兵器を開発していた」というものだ。森はこの情報はフェイクと判断したようだが、『微笑』の「栖方」を思わせるエピソードではある。
よく知られるように、アジア太平洋戦争期の少年雑誌には「殺人光線」を含む数々の新兵器が誌上で表現されていた。敗戦後のサブカルチャーの文脈では、一九五四年版『ゴジラ』や、一九五六年に連載が開始された横山光輝『鉄人28号』など、戦時中の日本で開発が進められていたとされる秘密兵器が世界の危機を救う、というモティーフがしばしば描かれてきた。そのように考えれば、『微笑』は、戦時と戦後を跨いで語られた「決戦兵器」をめぐるナショナルな想像力の系譜の中に位置づけられることになる。
わたしは横光作品のよい読者ではまったくないから、このテクストを横光の他の作品や発言とかかわらせて論じる力はない。だが、人々の行為や発話を意味づけていく価値基準や、出来事をとらえるパースペクティブ自体が大きく変化していた時期を物語現在とするこのテクストが、日本敗戦によって抑圧されたアジア太平洋戦争末期の「思想戦」と終末論的な想像力を、独特のしかたで再現=表象していることは確かだと思われる。こうした立場からの話題提供を通じて、専門家の方々の議論を少しでも活性化させることができれば、と願っている。