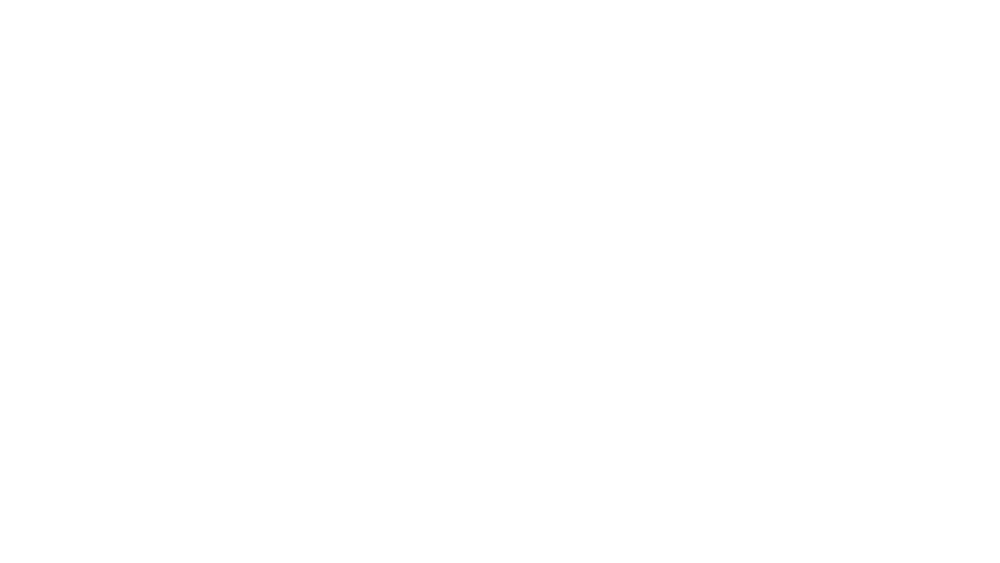日時 2022年3月26日(土)13:00
会場 Zoomによるオンライン配信
※立命館大学平井喜一郎記念図書館カンファレンスルームを中継会場としました。
協力 立命館大学衣笠リサーチオフィス・加藤周一現代思想研究センター
総会
開会の辞
特集 〈亡霊〉としての横光利一 ―西欧・アジア体験の衝撃と余波―
歿後七五年を迎える本年、横光利一を葬送するというのではなく、遺されたテクストのことばを聞き届けたい。なぜなら〈亡霊〉として回帰する存在が、繰り返し語り続けることばは、近代文学のアポリアとしてわれわれ自身の問いであり続けているからである。
ジャック・デリダのいう〈亡霊〉的存在は、死者と生者の合間に漂いながらわれわれに鋭い問いを投げかける。それはマルクスの存在が近代資本主義の続く限り更新され得ることを告げる。横光の文学的課題が、戦争と革命の二〇世紀とまともに向き合う中から生じたのだとすれば、それは戦後以降の時代を生きるわれわれの時代の問題であり続けているのだと言えるだろう。
文学的に、また人間的に、漱石のような横光山脈を想定することは難しい。だがそのこととは別に横光の課題を引き受けようとした戦後文学者たちが、その答えを明確に出来たとは思えない。完膚なきまでに批判された『旅愁』が、他方多くの読者を得た時代の空気を、われわれは正当に評価できてはいないのではないか。
本特集では、横光の問題性を批判的に継承しようとした戦後文学を再検討するなかで、未だ聞き取り得ないことばの行方を捜すことにしたい。今回は副題にもある通り、横光の西欧・アジア体験が戦後文学者たちに与えた衝撃と余波について取り上げていく。
敗戦前後の上海に滞在し日中関係を模索し続けた武田泰淳の姿勢、横光の歿後その半身を生きたとも言える川端康成、国際性の欠如を批判し西欧との対峙を課題とした加藤周一もまた横光の影を帯びているように思える。それぞれのテクストに回帰する横光の〈亡霊〉を総体として考察の対象としたい。
講演
講演者紹介 鷲巣力(わしず つとむ)氏 文筆家・加藤周一現代思想研究センター顧問
一九四四年東京生まれ。東京大学法学部卒。平凡社にて『加藤周一著作集』の編集に携わる。雑誌『太陽』の編集長を経て独立。著書に『加藤周一を読む』(岩波書店)、『「加藤周一」という生き方』(筑摩書房)、『加藤周一はいかにして「加藤周一」となったか 「羊の歌」を読みなおす』(岩波書店)、半田侑子氏との共編著に『加藤周一 青春ノート』(人文書院)がある。加藤周一現代思想研究センター(立命館大学)では加藤周一文庫デジタルアーカイブの整理と公開が行われ、作家以前の加藤の姿を知ることができる。「青春ノート」には横光利一への言及も見られることが注目される。
研究発表
藤原崇雅 戦後における武田泰淳の横光利一に対する評価
戦時下から戦後にかけて上海に居留した経験を持つことで知られる武田泰淳(一九一二~一九七六)は、横光利一作品に何度か言及している。本発表では、主に泰淳が記した評論「日本文学的命運」(『遠東観察者』一九四六・四)と小説『上海の螢』(『海』一九七六・二、四~九)をとり上げ、戦後において泰淳が横光をどのように評価していたのかを明らかにしたい。 「日本文学的命運」は泰淳が上海現地の雑誌に中国語で発表した、日本近代文学史である。注目すべきは、横光の代表作である『旅愁』(『文藝春秋』ほか、一九三七・四~一九四五・一)が高く評価されていることだろう。戦後は批判されることも多かった『旅愁』だが、泰淳は「日本の伝統精神へと回帰し」た横光の態度を、「複雑な問題をきちんと複雑な問題として分析し続け」(発表者訳)たものとして捉え直している。
この評価は、反動的な態度を擁護する立場から行われているのではない。なぜなら、「日本文学的命運」では転向文学および転向するという作家の身の振り方に、今後の日本文学の可能性が見出されているからである。泰淳は『旅愁』を転向文学の系譜に置くことで、文学者が社会状況に影響を受けていることの記録として評価しようとする。 また、泰淳は遺作となった『上海の螢』という長篇小説においても横光作品に言及している。この長篇は日中戦争末期の上海を舞台とする、泰淳自身と重ね合わせて読める人物が上海に居留した往時を回想していく物語である。この作品の語り手は、新感覚派の名作である『上海』(『改造』ほか一九二八・一一~一九三一・一一)を想起しながら散歩したことを回想する。しかし、その回想は「何かが、くいちがっている」という言葉から分かるように、上海の現実と横光が表象した物語中の上海とがずれてしまっていることの指摘となっている。
『上海の螢』は回想記的な形式を持つにもかかわらず、回想されるトピックが章を追うごとに散漫になっていくため、中心となる筋がうまく読み出せない。こうした書き方は、逆説的に回想が記憶の編集を経ていることに気づかせてくれる技巧ともとれる。小説がこうした技巧を使って書かれていることを踏まえるなら、『上海』への言及は都市やそこに居留する経験を表象する際、物語化が雑多な要素を捨象してしまうことへの批評として理解できる。
横光に対する戦後の評価としては、『旅愁』が戦争協力的な作品として批判され、『上海』は新感覚派の名作として位置づけられることが多い。一方で、泰淳の横光評価はこうした一般的な評価とは対照的である。横光の〈亡霊〉は、泰淳が移動や居留といった経験を踏まえつつ、自己の文学観の他者との異同を説明する際に現れるのである。
仁平政人 戦後の川端康成における横光利一 ―小説「自然」を手がかりに―
「僕は日本の山河を魂として君の後を生きていく」――川端康成による「横光利一弔辞」の、よく知られた一文である。弔辞において川端は、亡き友に語りかける形式で、自身と横光との差異と重なりを確認し、「新しい東方の受難者」としての「宿命」を負った横光を悼み、「君の後を生き」る自らの立場を示している。この文章は、同時期の他の発言とあわせて、川端における「日本(伝統)回帰」の宣言という文脈で読まれてきた。そしてそうした理解は時に、戦後の川端の歩みを横光の意志を継いだ、もしくはその〈亡霊〉に導かれたものとするような見方にもつながっている。だがその一方で、戦後の川端における横光との関わりについての詳細な検討は、なお十分に行われてきたとは言いがたい。
横光没後において川端は、『横光利一全集』(改造社)等の編纂や、「悲しみの代価」をはじめとした未発表草稿の調査・公表、また多くの解説・追憶文の執筆など、横光文学の流通や、その評価・作家イメージの形成に関わる活動に幅広く取り組んでいる。それとともに、「今もときどき横光君の何かの作品を読み返してみては、その未解決なものについて考へる」(「思ひ出二三」、一九六一・二)というように、横光文学との対話を長く続けている。それは一面では、戦後においても川端が前衛的な小説の試みを継続し、晩年に至るまで自らを「新感覚派」と規定していたことともつながっていると考えられよう。
だが、戦後の川端における横光との関わりは、以上の諸点に留まるわけではない。興味深いのは、複数の小説テクストにおいて、横光とのつながりを有する「死者」の形象が、奇妙とも見られる形で導入されていることである。なかでも短編小説「自然」(『文藝春秋』、一九五二・一〇)では、戦時下に特攻隊基地で「謎の死を遂げた」作家(語り手「私」の友人)に、横光と明らかに重なる設定が施されるとともに、自然/不自然、現在/過去、生/死、男/女…といった境界を流動化し攪乱するディスクールを通して、ある戦時中の記憶が語り出される。こうした同作のありようは、先行する川端のテクストと横光のテクストの双方に対して、批評的な側面を有するとみられるのである。本発表では、従来注目されてこなかった小説「自然」の検討を交えて、川端における横光の〈亡霊〉との関わり方について、「日本(伝統)回帰」という物語とは別のかたちで捉え直すことを試みる。